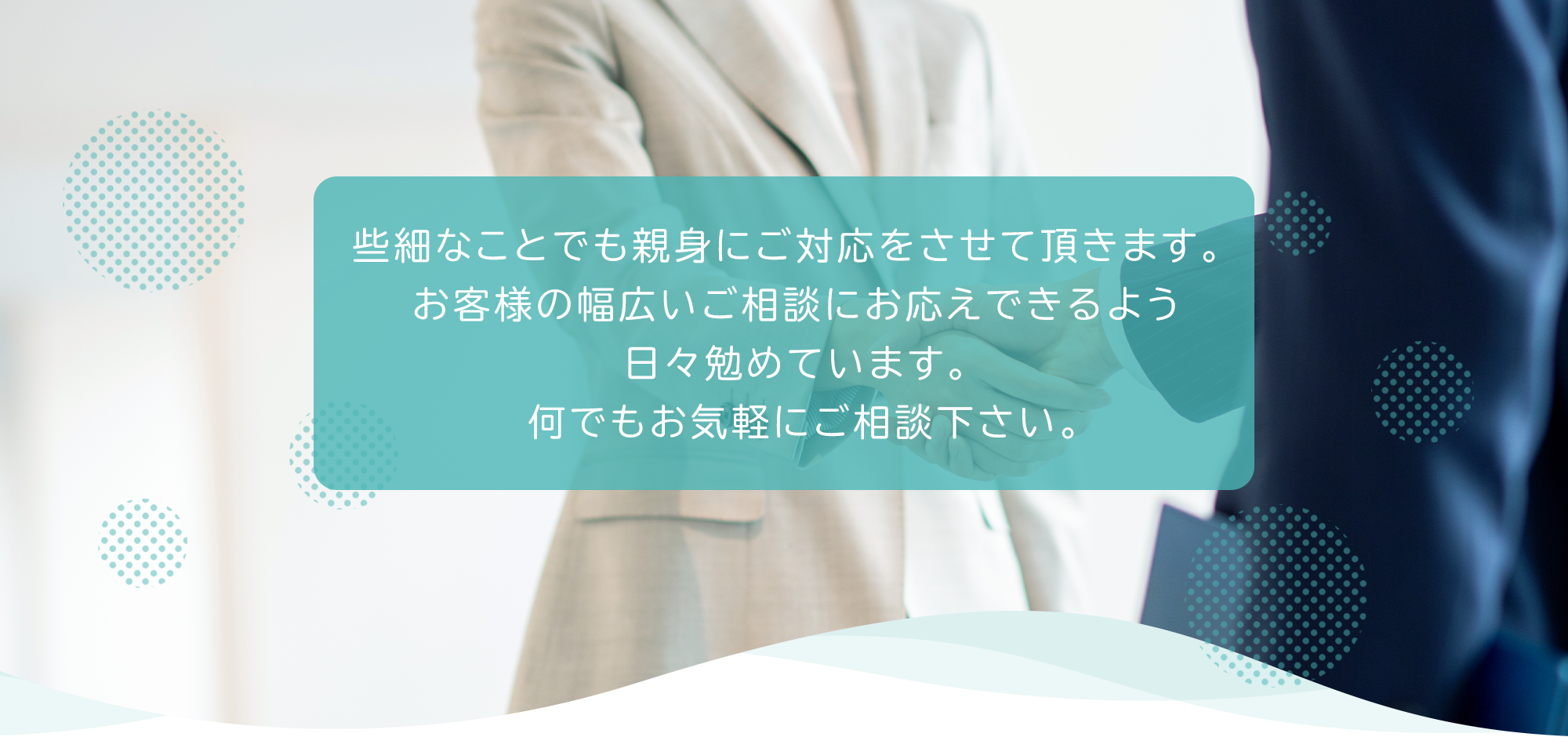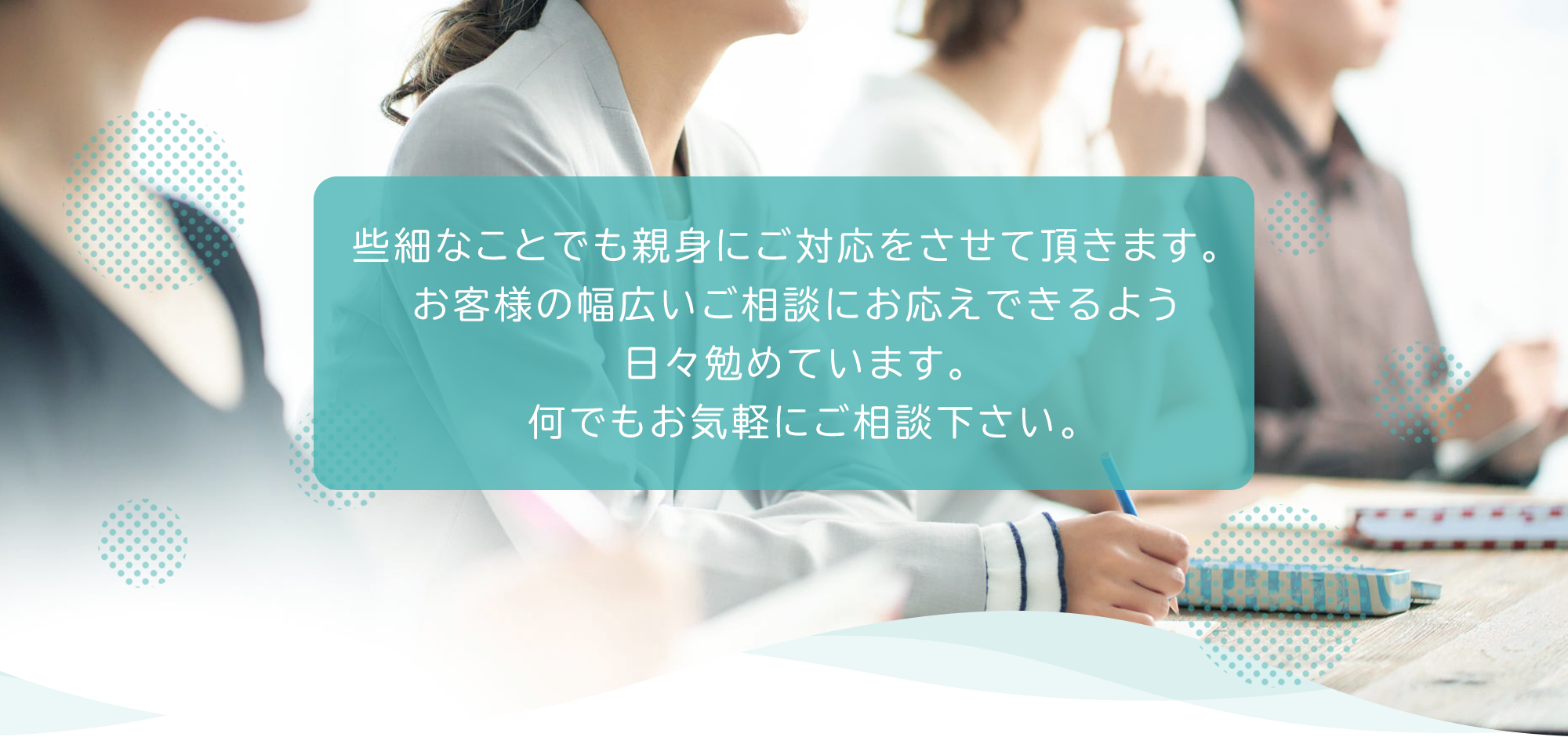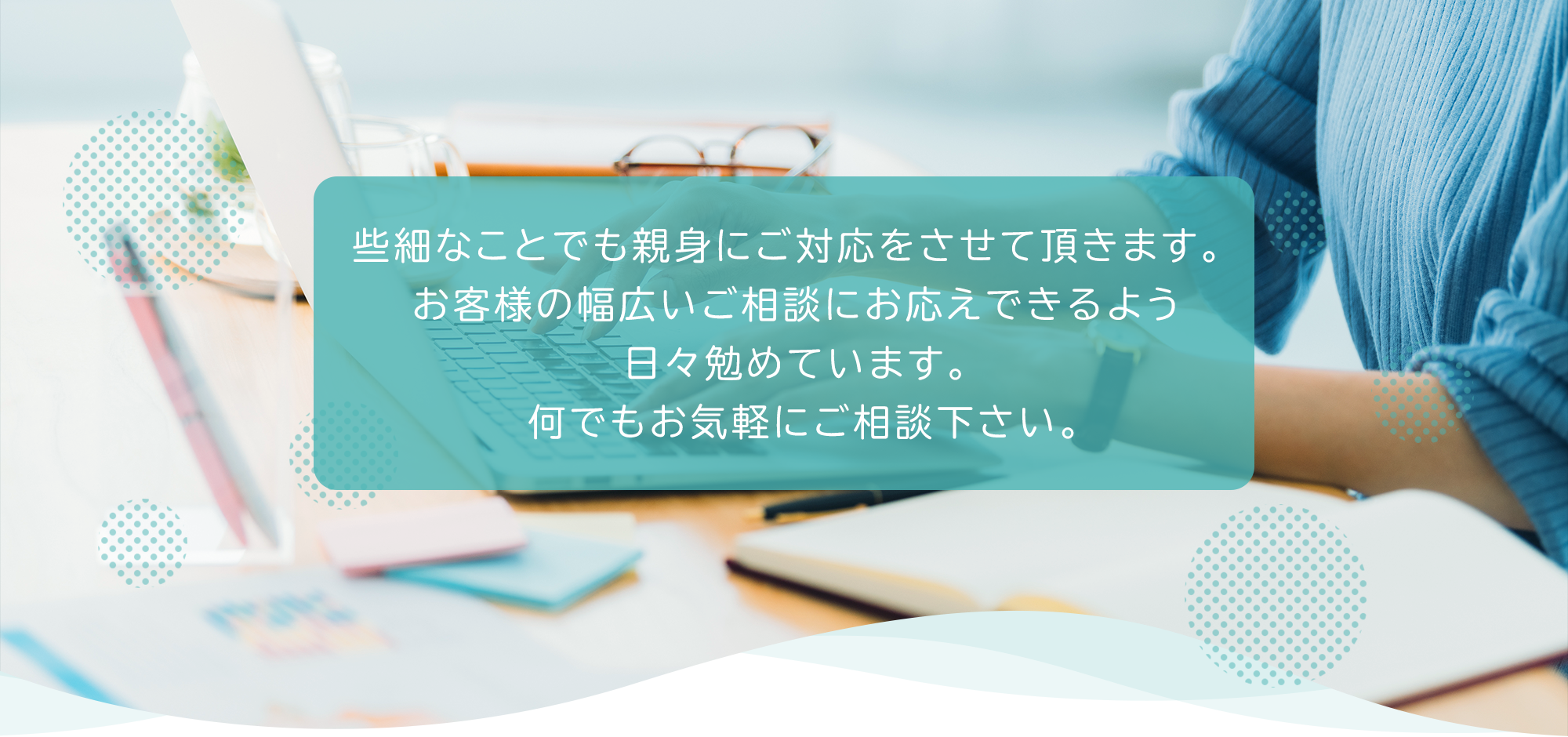News
ニュース
2023.07.31 ホームページをリニューアル致しました。
山本裕子税理士事務所では
小さな個人商店から、一般企業、不動産、相続まで、幅広いニーズに応えられるよう、日々、税務の研究に努めております。お客様の税務のお悩みから経営のお悩みまでお気軽にご相談下さい。当事務所は、顧客の良きアドバイザーを目指しています。
当事務所では、初回のご相談無料となっております。また、女性税理士ならではの細やかなご対応をさせて頂きます。お気軽にお問合せ下さい。
Service
業務案内
Office
事務所案内
| 事務所名 | 山本裕子税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山本裕子(やまもと ひろこ) |
| 所在地 | 〒253-0082 神奈川県茅ヶ崎市香川5-2-34 |
| TEL | 0467-86-0275 |
| FAX | 0467-87-5239 |